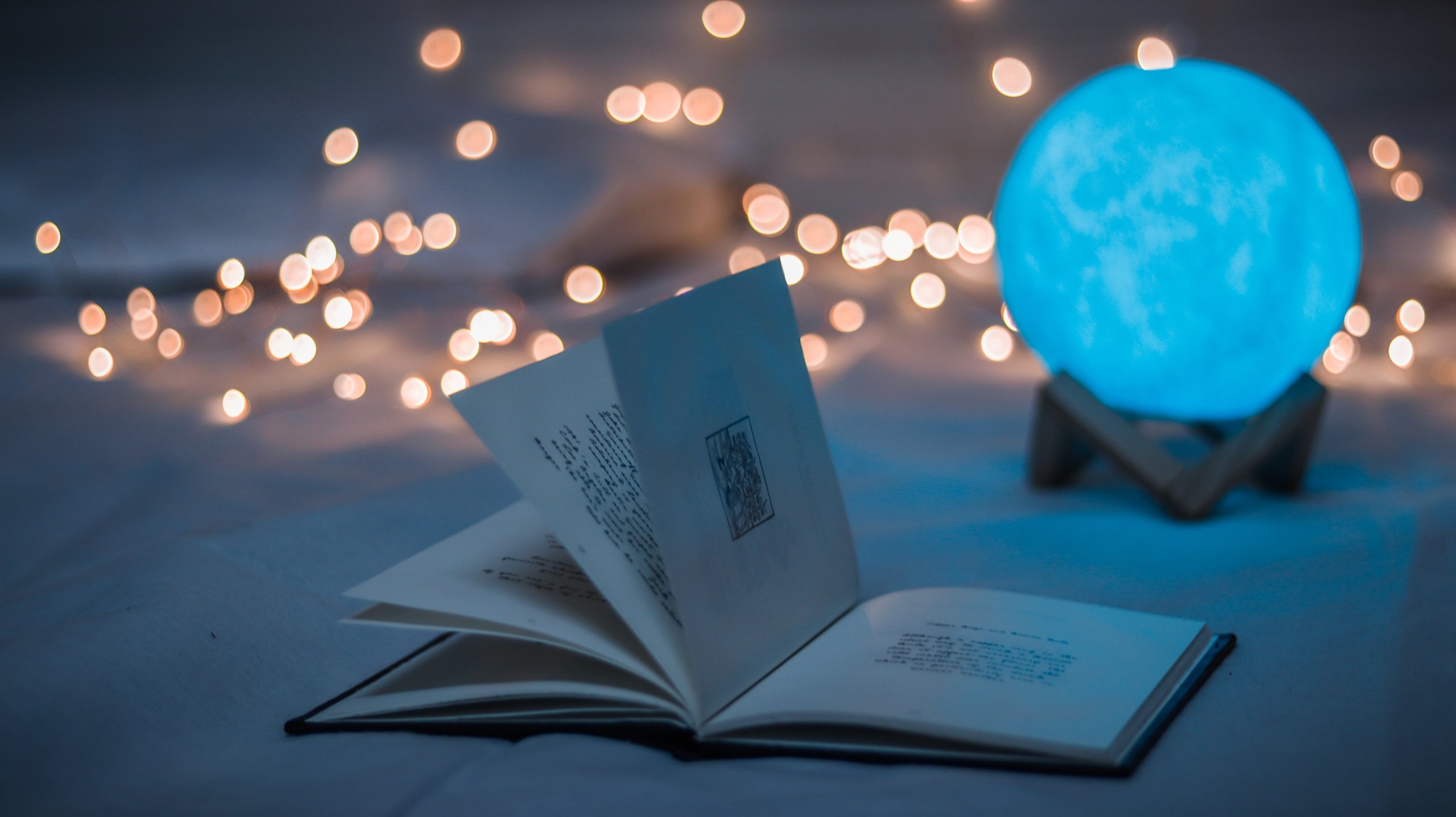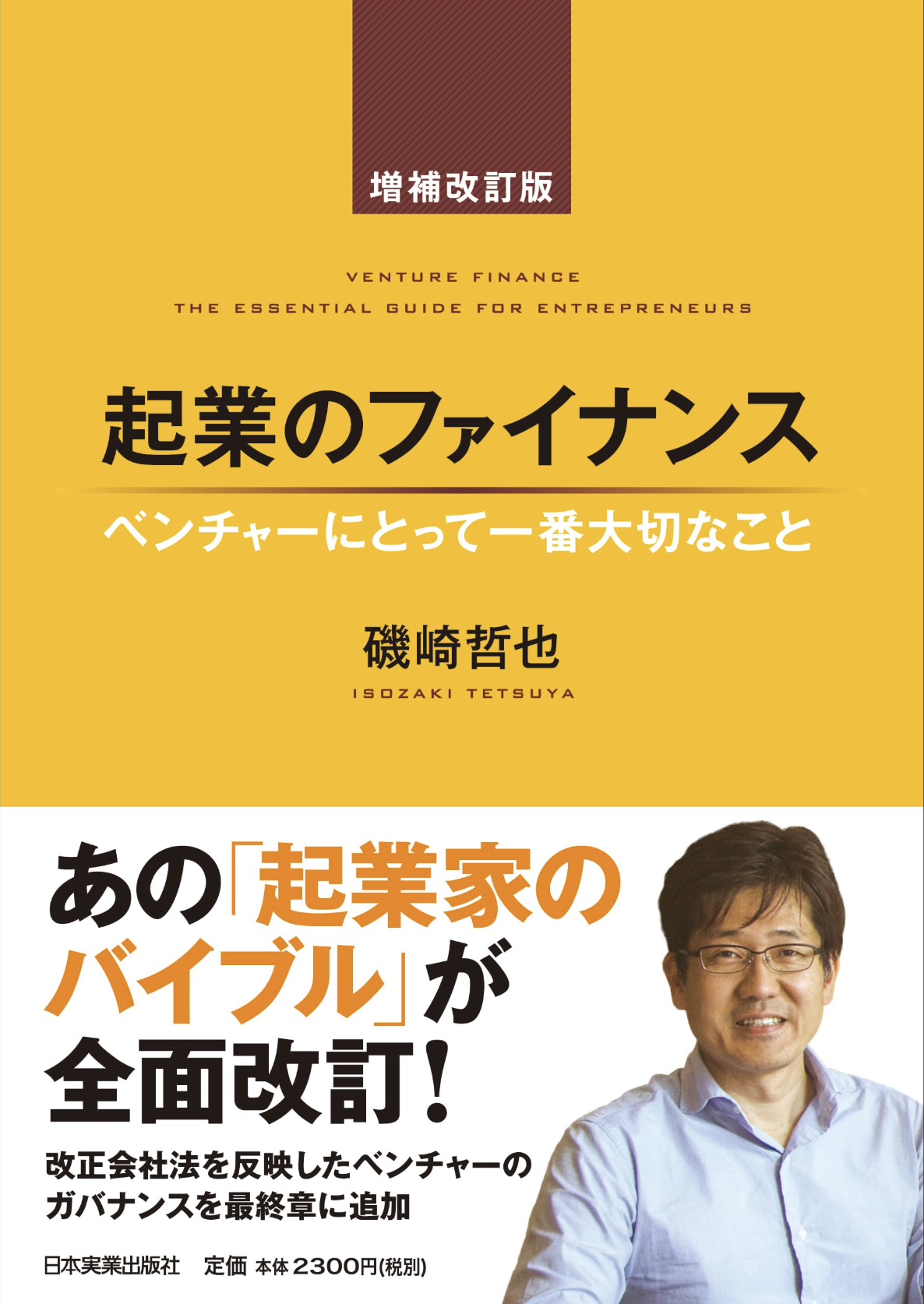
Memo
- 「歩は前に1つだけ進める」「飛車は縦横にいくらでも動ける」といったルールをいくら知っていても、上級者には勝てません。上級者はルールや定跡はもちろん、序盤から終盤までの「イメージ」をいろいろ持っているからです
- しかし、よく考えてください。金融というのは「お金が返ってきてナンボ」なわけです。
- 別の分け方として、 「(単に)起業して自分で事業をやっている中堅・中小企業」 と、「今までとまったく違った(イノベーティブな)ビジネスのやり方を志向する企業」 に分ける方法も考えられます
- 実際、成功者によるスタートアップへの投資はかなり行われてきています。ただしそれは広く一般には伝わらないのです。 なぜでしょうか? 自分でちゃんとビジネスの目利きができる投資家は、自分がどこに投資しているといったことを大声で言っても何の得にもならないからです。 世の中、「金が足りない」と思っている人はたくさんいますが、成功する人はあまりいません。 つまり、イケてないベンチャーがほとんどなわけです。ですから、「わたしはベンチャーにカネを出しますよ」といったことを言って、起業する人が大挙して押し寄せても、時間ばかりかかって実りは少ないわけです。イケてるベンチャーの情報は、イケてるルートを通じてイケてる投資家のところに必ず伝わってきます。
- 独立してさまざまな企業のやり方を見てきた人は、ベンチャーともコミュニケーションを取りやすいですし、何より、多数の企業の例を見て経験豊富なので、的確なアドバイスができることも多くなります。 ベンチャーを取り巻く社会というのは、特定の資源や取引先を囲い込むクローズドな社会ではなく、上記のようにさまざまな主体が関与するオープンな生態系です。起業が盛んな社会というのは、他の会社の中でも活用できるオープンな能力を持つ人やオープンな企業が多いほどうまくいくわけです。
- 例外を無視してあえてシンプルに言えば、ベンチャーはお金を借りるべきではありません。
- 人間は死んでしまったらそれで終わりです(「次の世界」があるかとうかはその人の宗教観によります)が、会社が死んでも、ファイナンスで最悪な選択肢を取っていなければ、そこでの経験やノウハウは、新しい次のビジネスの始まりにつながるわけです。 多くのベンチャー関係者が「事業計画どおりうまくいったベンチャーなんて見たことがない」と言います。 事業というのは極めて多くの要素が関連する「カオス」です。誰もやったことがないような画期的なビジネスを、ちっぽけな人間が完全に思いどおりコントロールできるなんて、おこがましいです。 失敗で反省するところは反省して、使える人材は適所でまた活躍したほうが、社会全体としても有益なわけです。 「成功しなかったこと」は「失敗」どころか、経験という価値が新たに付加されることなのです。
- 会社を設立した以降は、自分の欲望のためでなく「法人のため」「株主のため」「社会のため」になるかどうかを考える必要がある
- わたしは、ゼロから新しいものを造り上げるベンチャーの経営者には、ある種の強い「動物的欲望」が必要。自分が作ったサービスを誰もが使うようにしたい」とか「世界を変えてやる」といった、もうちょっと「公的」で「他者に働きかける」欲望です
- いくら高学歴で頭がいい人でも、演繹的に「自分が何をすべきか」の結論は出ないと思います。自分の人生なので何をやってもいいはずなのです。「これがやりたい!」「できるはず!」という根拠のない自情さえあれば。
- つまり、投資家をはじめとするベンチャーの事業に関わることになる人達は、(ソーシャルグラフという言葉を使うことは少ないと思いますが) 「こいつに本当に、この事業計画に必要な資金や人材を持ってこられるのかな?想定外のことが起こってもそれに対処できるのかな?」というところを見ているはずです。
- 人との出会いもそうですが、事業との「出会い」も第一印象は非常に重要です。 「成功しそうな経営者だ」と感じてもらうためには、事業の本質がイケているとか合理的な計画を持っているというだけでなく、経営者自身の「天性の魅力」のようなものも重要かもしれません。 特に、実績のあるベンチャーキャピタリストの人達は、口々に「計画が思いどおりにいったことなんか1回もない」「うちは「人』を見て投資をする」といったことをおっしゃいます。
- 「もしここで、期待するほどの需要が得られなかったらどうする?」「もしここで、ライバルが参入してきたらどうする?」というような話を、いろいろ頭の中であれこれシミュレーションする時に、事業計画はそのたたき台になると思います。 つまり、きれいな図表や分厚い事業計画書を作るのが重要なのではありません。事業計画を作ることを通じて考えがまとまっていれば、説得力のある話をできる可能性が高まるということです。→数字に落とす
- ターゲットとなる顧客が潜在的にどのくらいいるのか?
- そのうち、どのくらいが当事業の顧客になるのか?
- 顧客や商品当たりの単価はいくらくらいに設定するのか?
- 結果として売上がいくらになるのか?
- それに、どのくらい経費がかかるのか?
- 差引、どのくらいの利益が出るのか?
- 成功する事業家というのは、こちらが「この営業を行うのに何人くらいスタッフが必要なの?」「この技術はどうやってクリアするの?」といった質問をぶつけても、たちどころに「なるほど」という答えが返ってくることが多いです。 逆に、事業の根幹に関わる部分について、「ええと・・・・・」と詰まってしまったり、「それは考えてませんでした・・・・・・ね」といった答えが返ってきたりする場合は、あとから見ても成功していないケースが多い気がします。 やはり、成功する人は、事業のことを寝る間も惜しんで考えているので、「こうなったらこうする」といった不測の事態への対応や、成功して活動している事業のイメージも詳細に頭の中に描けているし、成功しない人は考えが浅い、ということではないかと思います。
- 重要なのは、自分が会社全体のその何%を持っているかという「率」であり、「株数」(個数)で考えるのは基本的にはナンセンスなのです
- つまり、一度株主になってもらったら、あとから「出ていってくれと言うことは非常に難しいので、どんな株主に何株持ってもらうかという「資本政策」は、設立当初から重に考えて策定することが重要です
- 創業者の持分は一度薄まったら二度と高まることはない、と考えておいたほうがよろしいかと
- 企業価値と利益の発生との間に「時間軸の違い」があることが原因です。つまりこれが、「投資家の目線」と「取引先や従業員等の目線」に差異が発生する原因でもあります。
- 社外取締役の役目は、経営陣と投資家の利害を一致させ、株主の目的、すなわち企業価値の向上を実現することです
- 企業の利害関係者全員がハッピーになっている「成功している未来」をイメージし、そこにたどり着くためには何をすればいいかを、投資家と経営者の間ですりあわせる仕組みこそが、コーポレートガバナンスだと考えます。
- そして、そのベンチャーが生まれるために最も大切であり、かつ、日本に一番不足している希少資源は、技術力でも、お金でもなく、「アニマル・スピリッツ」と、それを持ち合わせている「人」であるということを、繰り返し述べさせていただきました。 もちろん説得力のあるビジネスモデルやファイナンスのテクニックも必要ですが、それはまず「スピリッツ」が存在しないと意味がないわけです。
得たもの
- オープンな能力を持っている人は重宝される
- 希少な資源はお金よりも技術よりも、スピリッツ
- 事業計画を作ることよりも、事業計画を作ることで考えをまとめること
- 点のルールではなく、成功までのイメージを持つこと
ネクストアクション
- 下記を数字に落とす
- ターゲットとなる顧客が潜在的にどのくらいいるのか?
- そのうち、どのくらいが当事業の顧客になるのか?
- 顧客や商品当たりの単価はいくらくらいに設定するのか?
- 結果として売上がいくらになるのか?
- それに、どのくらい経費がかかるのか?
- 差引、どのくらいの利益が出るのか?
- 目の前の人を幸せにする、誇れる仕事をする